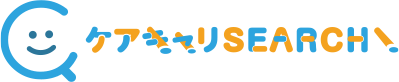- 介護求人・転職情報 ケアキャリサーチ!
- ケアキャリ!介護PRESS
- 介護のキャリア
- 働き方
- 介護サービスごとの夜勤の違いとは【4つのポイントで理解できる...
介護サービスごとの夜勤の違いとは【4つのポイントで理解できる】
高齢者の生活を24時間サポートする介護施設では、夜勤の仕事は欠かせません。
とくに特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホーム・グループホームなどでは、各施設の設置目的や規模の違いによって、夜勤の勤務内容で違いが生じます。
また同じ種類の施設でも「従来型」か「ユニット型」かで、夜勤の人員基準が変わります。
そこで本コラムでは…
・施設ごとの違い
・従来型とユニット型
・2交代制と3交代制
・休憩時間とその使い方
…の4点に着目しながら、介護サービスごとに夜勤の違いをみていきましょう。
施設ごとの違い
- 介護サービスの目的
- 入所者の条件
- 施設の設置基準
上記のような条件によって、利用者の要介護度や介護の内容・介護を担当する人数などが変わってきます。
まずは各施設の特徴と、施設ごとの夜勤の違いをみていきましょう。
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホームは社会福祉法人や地方自治体などが運営している公的施設です。
介護を必要とする高齢者の中でも、在宅での介護が困難な方を対象にした介護施設となっています。入所しているのは原則、要介護度が3以上の方です。
要介護度が高い方を対象とした施設なので、就寝中のおむつ交換や床ズレ(褥瘡 [じょくそう] )を防ぐための体位変換が必要な方もいます。
複数体制で夜勤を行う施設がほとんどで、仮眠室が設けられている割合も高いですね。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設(老健)は、
- 入院するほどではない
- 家庭で十分なケアを受けられない
…という利用者が、自宅で生活を送れるように回復を目指す施設です。
入居期間は原則3ヶ月から6ヶ月となっています。
老健は夜勤で複数体制をとっているところがほとんどです。
また9割近くの施設では看護師が配置されているので、医療的ケアが必要な際に看護師の指示を仰ぐことができます。
有料老人ホーム
有料老人ホームは、民間企業や社会福祉法人が運営する施設です。
1人以上の高齢者を入居させ、食事・身体介護・家事援助・健康管理のいずれかのサービスを提供する施設となっています。
また多くの有料老人ホームは、公共の介護施設より「サービス面」を重視しているのが特徴です。
規模や設備・職員の人員数は各施設によって異なります。したがって夜勤の勤務形態や休憩室の有無なども、施設ごとで違いが大きくなっています。
グループホーム
グループホームは医師によって認知症と診断され、要支援2以上と認定された65歳以上の方が対象です。
入居者の定員は1ユニットあたり9名と定められています。少人数のアットホームな環境のなか、認知症専門のスタッフが常駐して介助を行います。
認知症の方の行動特性もあって、夜勤では見守り業務が重要となります。
また介護業界ならではの慢性的な人手不足が影響し、夜勤は1人で行うことがほとんどです。
従来型とユニット型
夜勤の人員配置基準は「従来型」と「ユニット型」で異なっています。それぞれの違いについて、詳しくみていきましょう。
従来型
2000年以前には一般的だった介護施設は、4人部屋や6人部屋の「多床室」が当たり前でした。
多床室はプライベートを守るため、ベッドの間をカーテンや仕切りで区切っています。
しかし匂いや生活音などを含めると、十分とは言えない一面もあります(この人員配置を「従来型」と呼ぶことも)
なお夜勤帯の人員配置基準は下記の通りです。
- 利用者が25人以下 :夜勤の職員の数は1人以上
- 利用者が26人~60人 :夜勤の職員の数は2人以上
- 利用者が61人~80人 :夜勤の職員の数は3人以上
※それ以上の利用者数については省略
複数の介護職員で対応できるため、安心感があるのはメリットといえます。しかし多くの利用者を担当するため、そのぶん個別対応は難しいことがあります。
ユニット型
2001年以降に建てられた施設の場合、「入居者のプライバシーを保護する」という目的で、個室となっている「ユニット型」が厚生労働省より推進されています。
そのため比較的新しい施設ほど、ユニット型であるケースが多いです。今後もユニット型が増えていくと予想されています。
なおユニット型の夜間の人員配置は、2ユニットに対して1人以上となっています。
対応する利用者が従来型よりも少ないので、個別対応がしやすいです。しかしユニット単位でシフトを組むため、スタッフが休んだ場合に対応が大変になることもありますね。
2交代制と3交代制
夜勤の業務時間の区切り方は、主に「2交代制」と「3交代制」があります。それぞれの時間区分について、詳しくみていきましょう。
2交代制
2交代制の勤務時間例は以下のとおりです。
日勤・・・9時から18時
夜勤・・・16時から翌10時
3交代制
3交代制の勤務時間例は以下のとおりです。
早番・・・6時から14時
遅番・・・14時から22時
夜勤・・・22時から翌日6時
日本医療労働組合連合会が2019年に行った調査では87%の施設が2交代制を取り入れていました。
2交代制の施設では実働16時間以上、休憩は1時間から2時間程度という施設が多いようです。
休憩時間とその使い方
9割近くを占める夜勤の2交代制では、16時間以上の長時間労働になっています。
重労働になりやすい夜勤現場では、利用者の安全を守るために集中力を保つのが重要です。そのため夜勤時の休憩や仮眠は必要だと考えられています。
しかし慢性的な人手不足の介護現場で、十分な休憩時間は摂れているのでしょうか?詳しく解説していきしょう。
休憩時間
労働基準法第34条の第1項では、休憩時間について次のように規定されています。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を労働者に与えなければなりません。」
つまり2交代制で16時間以上続けて勤務する場合でも、法律上は休憩時間が1時間で問題ない…ということです。
そのため「休憩時間が2時間以上で仮眠室が設けられている施設」と、「人員不足のために1時間しか設けられていない施設」が存在することに注意しましょう。
休憩時間の使い方
労働基準法第34条の第3項で、休憩時間の使い方について次のように規定されています。
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければいけない。」
つまり休憩時間中は、利用者からのコール対応や見守り業務などをしてはいけません。
夜勤職員が複数配置されている施設では、休憩時間を交代で取ることができます。
しかし、1人夜勤が常態となっているグループホームなどでは交代の職員がいません。そのため法にのっとった休憩時間が取れていないケースもあるようです。
まとめ
夜勤の業務内容は、基本的にどの施設も同じで、以下の業務が大半です。
- 日勤からの引き継ぎ
- 夕食の準備・介助
- 就寝の準備とトイレ介助
- 寝たきりの入居者の体位変換・おむつ交換
- 見守り
- コール対応
- 起床後の着替えなどの介助
- 朝食の準備と食事介助
- 日勤への引き継ぎ
しかしそれ以外の勤務実態や労働条件は、働く施設によって違いがあります。
これから夜勤のある介護施設に就職・転職を考えている方は、ぜひ本コラムを参考にしてみてください。
 この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます。
この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます。
-
介護のキャリア
2018/10/24
 夜勤で月収◯万円UP!? 介護職の夜勤の働き方と1...
夜勤で月収◯万円UP!? 介護職の夜勤の働き方と1...
-
介護のキャリア
2020/06/10
 介護職に向いてる人は?現場で求められているのはこん...
介護職に向いてる人は?現場で求められているのはこん...
-
介護のキャリア
2018/05/25
 介護職が夜勤を行う3つのメリット
介護職が夜勤を行う3つのメリット
 オススメの介護求人情報
オススメの介護求人情報
ケアキャリサーチ!がオススメする、今注目の介護求人情報です。